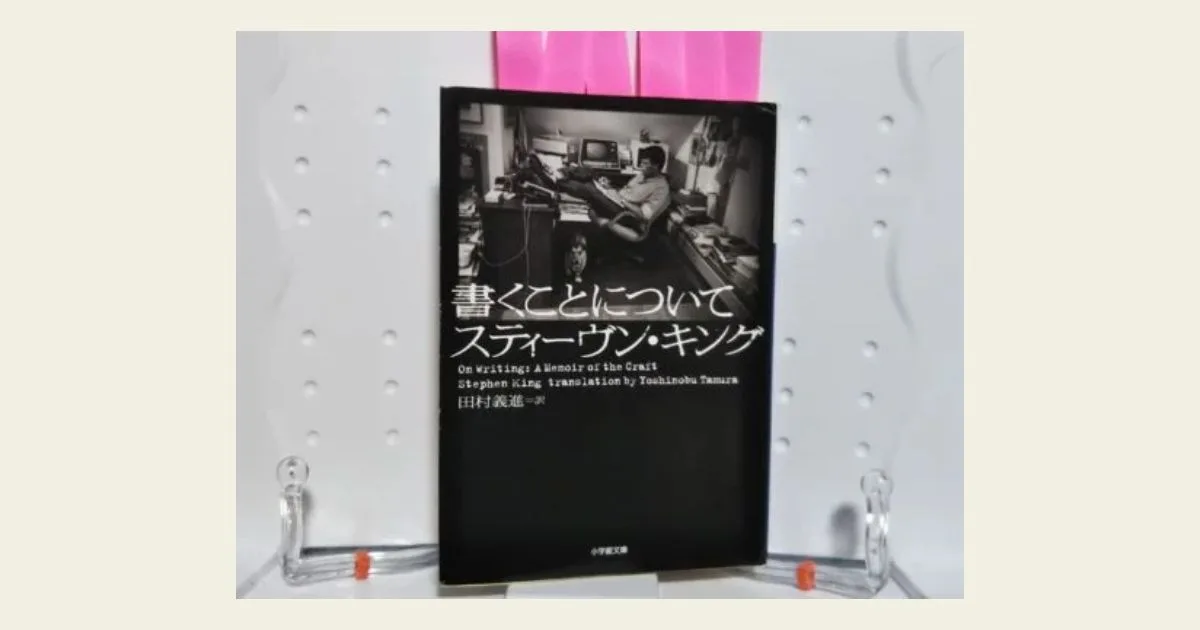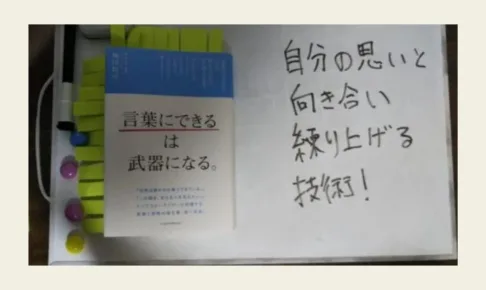長編小説「ミザリー」や「シャイニング」、そして映画「スタンド・バイ・ミー」の原作小説を生み出した小説家スティーブン・キングは、小説の書き方について自伝的にまとめた『書くことについて(訳 田村義進 小学館)』という本を出しています。
物書きとしての成長を目指していた私は、ストーリー性や小説構成も学ぶもの面白そうだなーと思い本書を購入しました。
本書は小説の書き方だけでやなく文法の使い方、そして文章を削ることがいかに重要であるかを解説してあります。小説家志望の方はもちろんのこと、Webライターといった文章を書くことを生業にしている方にとっても、非常にためになる内容となっていました。キング氏のフランクな語り口調と生き様も相まって、学びながら楽しく読むことができます。
本記事では、名著の1つである「書くことについて」の感想をまとめました。
Contents
スティーブン・キングの生き様・小説技術を学ぼう
言葉については誰も何も尋ねようとしない。トン・デリーやジョン・アップダイクやウィリアム・スタイロンのような純文学の作者には尋ねても、通俗小説の作家には尋ねようとしない。だが、われわれ三文文士の多くもまた、及ばずながら言葉に注意に意を注ぎ、物語を紙の上に紡ぎ出す技と術に心を砕いている(P8~9)
「書くことについて(著 スティーブン・キング 訳 田村義進)」より引用。
「書くことについて」の構成は、巨匠スティーブン・キングの子供時代から語られる自伝パート、小説家としての「技術や考え方」を指南する文章読本パートの2つがメインです。
そして最後章では本書の執筆中に巻き込まれた事故のこと、その事故や本書執筆を通じてキング氏が気づいたことについて語っています。
私が「書くことについて」を読むきっかけとなったのは、精神科医や映画評論家としても有名な樺沢紫苑(かばさわしおん)氏の著書「読んだら忘れない読書術」や「アウトプット大全」内で紹介しているのを目にしたからです。
ビジネス書、インターネット関連書、その他樺沢が影響を受けた珠玉の10冊『書くことについて』
「読んだら忘れない読書術(P241)」より引用
スティーブン・キングは、自らの小説作法についてまとめた『書くことについて』(小学館)の中で次のように述べています。
「アウトプット大全(P126)」より引用
樺沢氏の著書で記載してある、「作家になりたいのなら、たくさん読んで、たくさん書くことしかない」という文言に惹かれました。
「書く」という基礎を学んでいきたい当時の筆者にとって、書くことについてを読むことは、新たな気付きになると感じたのです。
「履歴書」で見るスティーブン・キングの半生
自叙伝ではない。どちらかというと、「履歴書」に近い。
ほとんどの人間は多少なりとも作家やストーリーテラーの才能を持っている。そういった才能は磨き、膨らませることができる。そうでなかったら、このような本を書く意味はない。(P16)「書くことについて(著 スティーブン・キング 訳 田村義進)」より引用。
以下、引用は同書からです。
スティーブン・キング氏本人が「子供のころは楽ではなかった」と語っている通り、幼年時代から続くスティーブン・キング氏の波乱万丈の人生を、第一章では存分に見ることが出来ます。
読み進んでみると、これが本当に波乱万丈。しかし、悲壮感を漂わせない軽妙な言い回しやブラックジョークが畳み掛けてくるおかげで、一冊の小説を読んでいるかのように惹き込まれました。
「もっと良いものを、自分で書きなさい」と言った母の言葉。
文章を削ることで世界が広がった経験。
デビュー作「キャリー」の主人公が好きではなかった中で、ある女生徒の悲しい境遇を重ねることで理解したという経験。
後の妻となるタビーとの出会い。
麻薬や酒に溺れながらも、「ミザリー」や「トミーノッカーズ」を書き上げたこと。
どれもが私の心に残るエピソードでした。
「書くことについて」では各エピソードをなぞりながら、小説家スティーブン・キングがどのようにして誕生したかを知ることができます。
どのような状況に陥っても作品を生み続けた、キング氏の精神力に脱帽です(麻薬は駄目すぎるけど)。
実践的な小説作法は第2章からですが、「一体どのような人物が小説講義をしてくれるか」を第1章を通じて知ることで、「書くことについて」の内容がより記憶に残ると思います。
小説家の「道具箱」に入れるべきものとは
スティーブン・キング氏がなぜ「道具箱」という表現を用いるかというと、まだ幼かったキング氏と大工であった伯父オーレンとの間に、大工道具箱に関するエピソードがあるからです。
伯父はドライバー1本だけで作業に事足りるのを知りながら、ドライバーだけではなく道具箱ごとキングに持ってこさせるよう言いました。キング氏がなぜ道具箱ごと必要になるのかと聞くと、以下の言葉が返ってきました。
「ここに来てみなきゃ、ほかにどんなことをしなきゃいけないかわからない。だから、道具はいつも一式持っておいたほうがいいんだよ。そうしたら、予想外のことに出くわしても、おたおたせずにすむ」
「書くことについて」(P149)より引用
大工であったオーレンの言葉を「物書き」にも当てはめ、道具箱と形容しているのですね。以下では実際に、スティーブン・キング氏が提唱する「小説家の道具箱にしまっておくもの」を見ていきましょう。
道具箱の最上段にしまうものその1.語彙
よく使うものはいちばん上の段に収納する。この場合は文章の糧、すなわち語彙である
「書くことについて」(P150)より引用
物書きとして一番必要になるのは語彙というのが、小説家スティーブン・キングとしての主張です。
しかし重要なのは語彙の量ではなく、「その語彙をどう使っていくか」にあると解説しています。
本書では「語彙が豊富な作家の文章」と「簡単な語彙だけを使うことを好む作家の文章」がどちらも載せられており、どちらも素晴らしいのだとキング氏と述べています。
やってはいけないのは、語彙の少なさを言葉の多さでごまかすことで、ごまかすくらいなら簡単な言葉で表現すべしというのがキング氏の持論となっているのです。

安易なレトリックを使わないほうがよいという意見は、日本のコピーライターとして有名な梅田悟司(うめださとし)氏の著書『言葉にできるは武器になる。』でも解説されています。
道具箱の最上段にしまうものその2.文法
文法をおろそかにするということは、文章をおろそかにするということである。
「書くことについて」(P160)より引用
詳しい文法学習は専門書に譲っていますが、「書くことについて」ではキング氏の「これだけは説明したい」という部分が凝縮されています。
本書で紹介されている文法の使い方は英語がベースであり、あくまで小説での使い方ですが、その論理はライターやブロガーにとっても学ぶべき点が多かったです。
とくに「~される」の受動態より「~する」の能動態を使うべきであったり、まずは主語と動詞の基本文を抑えるべきであったりなどは、読まれる文章の基本となる考え方だとも思います。
さて、個人的なこの章の見どころは、スティーブン・キングの「副詞嫌い」ですね。とにかく余計な副詞に対するアンチっぷりが凄まじい。
ここはぜひ本書を手にとって読んでみてください。
スティーブン・キングにとっての「書くことについて」とは
作家になりたいのなら、絶対にしなければならないことがふたつある。たくさん読み、たくさん書くことだ。私の知る限り、そのかわりになるものはないし、近道もない。
「書くことについて」(P192)より引用
書くことについてという書籍のタイトルと同じということもあり、ここは「小説家スティーブン・キング」の小説への考え方が色濃く出ている章です。
小説にプロットはいらない、リサーチはリアリティを与えるがそこまで必要ないといった考え方は、まさにキング氏独特の考え方ではないでしょうか。
普段から小説を読んだり、書いたりしている方にとっては、多くの発見がある「絶対に読むべき文章」となると思います。
また、「脚本を書くための101の習慣」で22人すべての脚本家が必要であると言っていた、「最後まで書ききること」「リライトは必ず行い、第三者の意見をもらうこと」についても語られています。
キング氏の場合だと妻のタビーが、主に第三者の視点としての役割を果たしていますね。

スティーブン・キング氏が力説する「文章を削ること」とは
本書でとくに語られているのは、文章を削ることの大切さです。スティーブン・キング氏は「書くことについて」の中で、次のように語っています。
私に言わせるなら、優れた描写というのは、すべてを一言で語るような、選びぬかれた少数のディティールから成り立っている。
「書くことについて」(P232)より引用
「書くことについて」(P297)より引用
「最愛のものを殺せ。たとえ物書きとしての自尊心が傷ついたとしても、駄目なものは駄目なのだ」
このように述べるほど、キング氏は余計な表現をなくすことを全編に渡り推奨しています。
「書くことについて」以外の本でも、いわゆるリライトや推敲、校正については大切であると紹介されています。それは小説においても例外ではないということです。
とくにキング氏は、過去に出版社で「第2稿は初稿から10%文章を削る」という教えを学べたことが、あらゆる講義や授業よりも有益であった語ってるほど、文章を削ることを重要視しています。

生死の境をさまよって気づいた「生きることについて」とは
一言で言うなら、読む者の人生を豊かにし、同時に書く者の人生を豊かにするためだ。
「書くことについて」(P358)より引用
(中略)
おわかりいただけるだろうか。幸せになるためなのだ。
キング氏は本書「書くことについて」をまだ書き終えていない時期に、車に轢かれるという事故にあっています。
これが非常に大きな事故でして、キング氏は生きているのが奇跡であるほどの怪我を負い、しばらく執筆が不可能でした。
その生死をさまよった経験から、今一度「生きること」や「書くこと」に向かい合って考えたことが第4章で語っています。
その経験の末に手にした、「書くために生まれてきたのだ」を始めとする、小説家スティーブン・キングが手にした答えを、この章で知ることができるのです。非常に読み応えがありました。ぜひ本書を手にとってお読みください。
小説だけに留まらない「書くことについて」を学んで
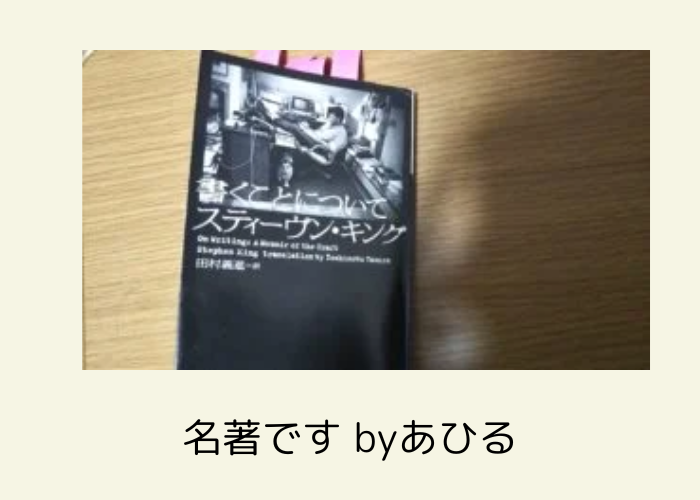
「アウトプット大全」や「読んだら忘れない読書術」で知ったこの「書くことについて」ですが、めちゃくちゃ面白かったです。
母子家庭、二人兄弟、工場勤め経験があるという筆者と同じような境遇であったので、勝手に感情移入しながら読んでいました。良書の紹介から新しい良書に出会えることも、読書の醍醐味の1つです。
「書くことについて」は小説を書いている方にはもちろん、文章に関わっている方全員におすすめできる本と言えます。